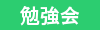海外の電力事情パート1(2014年11月6日)
第1回目は海外の動向を知ることが日本の今後の方向性をつかみ、未来を占うことになるとみて、欧州4か国と米国の現状を調べることにした。今回の勉強会で学んだことを、電気事業体制、電力供給体制、電源構成、自由化の動向の4項目に絞って、5か国の差異がわかるように下記の表にまとめてみたが、欧米諸国も常に状況は変動しているので、今後のフォローアップは欠かせない。各国電力事情
英国  |
フランス  |
ドイツ  |
スウェーデン  |
米国  |
|
| 電気事業体制 |
発電会社 イノジーホールディングス社 パワージェン社 ニュークリアエレクトリック社 他125社(2013年6月時点) 送電会社 ナショナルグリッド社 SPT社(スコティッシュパワー社の子会社) SHET(スコティッシュサザンエナジー社の子会社) 配電会社 12社(元配電局)、他2社 小売会社 107社 |
発電事業者 EDF(旧フランス電力公社、現フランス電力会社):フランス発電量シェア80% CNR(仏GDFスエズ社系) SNET(独E.ON社系) 送配電 EDFの法的分離(子会社化)→シェア約95% RTE:送電部門(2005) eRDF:配電部門(2008) 地方配電事業者:約160社→シェア約5% 小売事業 電力自由化前:EDFと地方配電事業者(160社)が独占 電力自由化後:新規参入業者(約20社)も追加: →EDFに対抗しシェアを伸ばす(2012年時点) →産業用・業務用:20.8% →家庭向け:7.2% |
発電企業 E.On RWE EnBW Vatternfall 送電会社 Amprion 50Hertz Tennet TSO TransnetBW 配電会社 送電会社4社傘下の計940社 |
発電会社 バッテンファル社 E.ONスウェーデン社 フォルトゥム社 送電会社 スペンスカ・クラフトナート社 配電会社 約170社 |
3,200社以上の電気事業者が存在し、①私営②連邦営③地方公営④協同組合営の4つに分類。 ①私営は約200社。全米販売電力量の約6割を占める。1990年代の自由化までは発電から小売までの垂直統合体制で地域独占だったが、自由化後は分社化や送配電事業に特化するなどの動き。 ②連邦営は9社。水力発電開発と発電電力の卸売りが主な事業。 ③地方公営は約2,000社。州や地方自治体が主に所有。大半は小規模の配電事業者だが、一部発送配電を一貫して行う大規模事業者も存在(サクラメント電力公社、ロサンゼルス水道電力局など)。 ④協同組合営は約900社。農村地方の住民やコミュニティが組合員となって設立し、主に組合員向けの電力供給を行う。大部分が配電専業となっている。 さらに、自由化の進展により、独立系発電事業者(IPP)やパワー・マーケターなどの「非電気事業者」も電力事業に携わっている。 |
| 電力供給体制 |
発電(128社) ↓ 卸売(「取引所取引・相対取引」「需給調整市場」「系統運用者」) ↓ 送電(3社) ↓ 配電(14社) ↓ 小売(107社) ↓ 需要家(2,500万件) |
発電[EDF]+[CNR、SNET(新規参入)] ↓ 卸売[相対取引]+[取引所取引(EPEX)] ↓ 送電[RTE(EDF子会社)] ↓ 配電[eRDF(EDF子会社)]+[地方配電事業者] ↓ 小売[EDF]+[国内外の小売供給事業者] ↓ 需要家 |
発電(4社) ↓ 卸売(相対取引、取引所取引-EPEX) ↓ 送電(4社) ↓ 配電(940社) ↓ 小売(発電4グループ、自治体運営電力会社、トレーダー、大口需要家など) ↓ 需要家 |
発電(大手事業者・自治体営事業者) ↓ 卸売(相対取引・取引所取引) ↓ 送電 ↓ 配電(約170社) ↓ 小売(大手事業者・自治体営事業者) ↓ 需要家 |
【地域送電機関(RTO)を設置している地域】 発電(「電気事業者の発電部門」「IPP」) ↓ 送電・卸売(「設備所有」「系統運用」「市場運営」「電気事業者の送電部門」「RTO」「取引市場」) ↓ 配電(電気事業者の配電部門) ↓ 小売(「電気事業者の小売部門」「マーケター」) ↓ 需要家 【垂直統合体制を維持している地域】 発電(「電気事業者の発電部門」「IPP」) ↓ 送電(電気事業者の送電部門) ↓ 配電(電気事業者の配電部門) ↓ 小売(電気事業者の小売部門) ↓ 需要家 |
| 電源構成 |
2012年時点:火力69%、原子力19%、水力と再エネなど13%。 火力の内訳として、全発電設備比で石炭が39%、ガスが28%、石油が1%となっている。石炭火力からガス火力への転換が進んでいる。 |
2012年時点:火力約22%、原子力約49%、水力約20%、再エネ約10% 2013年原発設備58基(6,300万kW): 発電量シェア約75% 火力の内訳:石炭6%、ガス8%、石油7% (全ての発電設備との対比) |
2011年時点:火力60%、原子力18%、水力3%、再エネなど19% 火力の内訳として、全発電設備比で石炭が45%、ガスが14%、石油が1%程度となっている。2020年に再生エネルギーの発電比率を約35%まで引き上げる計画。 |
2011年時点:水力が44%、原子力40%、化石燃料3%、再エネ13% 水力偏重の危険性として、渇水や厳冬の場合水力使用不可となるケースも出てくる |
2011年時点:火力約68.5%、原子力約19%、水力(揚水含む)約7.4%、再エネなど5.1% 火力の内訳は、全発電設備比で石炭が43.4%、ガスが24.2%、石油が0.9% |
| 電力自由化動向 |
1990年から段階的に進み、1999年以降、家庭用を含めた全需要家が電力の購入先を自由に選べる 競争激化で料金メニューの数が増大したほか内容も複雑化 需要家はどのメニューを選択すればいいか判断に迷う事態も出てきている 規制当局は料金の比較が容易にできる仕組みを電力各社に提案している 電気料金は上昇しており、2013年は2004年比で約2倍 |
電力自由化法の設立(2000年2月) →EU電力自由化指令で既に自由化済み(1999年2月から) 段階的な自由化 市場開放率:約20%(99年2月)→約30%(00年5月)→約37%(03年2月) 産業用・業務用の自由化(04年7月) 全面自由化(07年7月) 一方で規制料金体制も併存 →自由化権利の行使後も、家庭用需要家のみ規制料金への復帰も可能(07年7月~) 電気料金は自由化後も安定的 →原発比率が高いため、燃料費高騰の影響が小さい →他の欧州諸国と比で最も安い部類 |
1998年に新たなエネルギー事業法が施行。家庭用も含めた全面自由化が実施された。発電シェアは、自由化当初こそ4大事業者が8割を占めていたものの、再エネ事業者の拡大、脱原子力などにより2012年には46.9%まで低下 卸電力取引活性化に向けた動き。2000年、フランクフルトに欧州エネルギー取引所(EEX)が、ライプチヒにライプチヒ電力取引所(LPX)がそれぞれ設立された。しかし、取引量が伸び悩み、2001年10月に両取引所の合併。2002年にライプチヒで合併後の取引所が運用を開始 その後、2008年、フランスの電力取引所(EPEX)と運用を統合し、スポット取引はパリ、先物取引はライプチヒにそれぞれの業務を集約。取引量は年々増加。2011年の1日前市場での取引量は2,246億kWhに達した 電力料金はEUで最も高い部類。燃料価格の上昇、環境税引き上げ、再エネ買取コストの増大、CO2排出権取引の開始などが要因 2013年時点で一般家庭の再エネ電源導入による負担増は月額で15ユーロ(約1,950円)と、電気料金の約2割を占める |
1992年に国家電力庁が100%国有企業に改組されると同時に同庁が管理していた送電系統を分離。スペンスカ・クラフトナート社が設立され、発送電が分離された 1996年から送配電ネットワークの利用を第三者に開放、自由化が開始された。電力会社間取引、家庭も含め電力会社の選択が可能となった |
1992年のエネルギー政策法により、新たな発電事業者としてIPPが規定。自由に発電施設を所有、運転し、電力販売も可能になり、全米で実質的に自由化の動きとなった 連邦エネルギー規制委員会(FERC)は卸電力市場の競争促進を図るため、1996年にオーダー888・889を発令。発送電部門の分離、送電線の開放などを電力会社に義務付けた 小売については、2013年10月時点で全米50州のうち13州およびワシントンDCで小売の全面自由化を実施中。当初は、最大24州とワシントンDCで自由化実施の法律が成立したり、規制が制定されたものの、2000~2001年のカリフォルニア大停電によりカリフォルニア州は2001年9月に小売競争を中断した |