|
補助金動向に一喜一憂した2023年国内市況。2024年をどう見るか、商社や広域系ディーラー、地場ディーラーなどの声や元売りの動向などを各地区でまとめた。
【北海道】ENEOSは広域ディーラー向けの販売枠を今年3月まで前年比10%削減と通知している。さらに、為替の円安ドル高基調が強いうえ、現行の補助金制度が4月まで続く予定のため、輸入に二の足を踏む状況だ。加えて年々内航船が逼迫しており、供給面はタイト。昨年10月には北海道への転送が困難になった灯油が京浜地区で溢れ、京浜市況を押し下げる一方、北海道の市況は下支えされた。
また4月からは働き方改革関連法で、トラックドライバーの時間外労働の上限が規制される。2024年問題対策として、北海道では運賃の改定、チャーター便による安定的なローリー確保を行う卸業者が多いようだ。しかし、そのうえで懸念されるのが大雪による配送の混乱だ。広域系の一角は「2024年は配送困難がさらに顕在化するのではないか」と危惧する。また、商社系ディーラーは「運送会社などの対策の度合い次第で大きな差が生じかねない」と述べていた。
気象庁によると、1~2月は北海道の気温が高くなる見込みで、さらにエルニーニョ現象が4月まで続く見通し。今冬は暖冬傾向が強いとされ、灯油需要の懸念材料となる。
【東北】小売市場の特約店、SSの統廃合が進んでおり、2024年もこの動きがさらに加速する可能性がある。これは他地区でも水面下で進んでいるが、こと東北地区ではこの流れが速い傾向が強い。現在、石油業の経営者の事業継承が後継者難で進まないことや、都市部以外のSSで販売減少、人材不足で運営が成り立たないケースが増えていることが背景にある。実際、域内の経営者によると、このようなM&Aやそれにかかわるコンサルタント業からの打診が増えていると伝えているという。
昨年10月に岩手県を本拠に宮城県、秋田県で19カ所のSSを運営する出光興産特約店の中川石油が子会社の出光リテール販売と事業を統合。
また、11月に都市部以外では山形県白鷹町でENEOS特約店の松下商店と出光興産特約店のカク上山口商店、佐藤燃料店の3社がSSを1店舗に集約し、「マイスリー白鷹」として運営を開始するなど、系列の垣根を超えた動きも見受けられた。
【京浜】2023年は補助金政策の動向で市況が動く官製相場の側面が強かった。複数の市場関係者からその時々で「需給より補助金予想が材料」と言い切る声も寄せられていた。
2024年問題と補助金の出口戦略が関心事
補助金支給は4月30日に終了すると政府は発表しているが、市場関係者の多くは半信半疑だ。昨年11月にはトリガー条項凍結撤廃の是非が国会で取り上げられた。4月30日はゴールデンウィーク期間で、行楽シーズン真っ最中にガソリンや軽油の小売価格が大きく変動する可能性を秘めている。2008年のトリガー条項発動と再凍結による小売市況の混乱、2011年の東日本大震災後のSS行列などは記憶に新しく、今回も変動幅次第ではGW期間にSSへ車の大行列ができる公算が大きい。すでに商社などは在庫の積み上げ有無、一般社会の風向きなど、一大商機に向けて調査や準備を進めている。
また、4月から建設、物流、運送、医療業界などで時間外労働の上限が規制される。いわゆる「2024年問題」で、燃料を運ぶローリー業者、さらに軽油消費側の陸運やバス業界に影響が出るのは必至。すでに先行して運賃の値上げや走行距離の見直し、減便などが業界内で話題となっているが、4月以降はより本格的となり、軽油大消費地の首都圏で需給が大きく変化する可能性もある。
製油所のあり方は2024年も課題に
2023年には製油所や油槽所の流通合理化として、元売り間バーターの見直し、スポット出荷量の調整、ないしはそうした動きの探り合いが京浜地区でも見受けられた。大枠では、ENEOS和歌山製油所が昨年10月に精製事業を停止、出光興産の山口製油所も今年3月に精製事業の停止が予定されている。
元売り間では、ENEOSは韓国大手SKイノベーションと精製設備の協業で合意した。出光興産は日量12万バレルの山口製油所を含め、2030年までに30万バレルの精製能力削減を打ち出し済みだが、山口製油所以外の削減対象製油所やトッパーは現在も検討中だ。
コスモエネルギーHDは大株主の旧村上ファンド系から製油所の合理化などが指摘されていたが、昨年12月に旧村上ファンド系所有株をLPG販売大手の岩谷産業が買い取り、同社が筆頭株主に移行した。その結果、製油所のあり方はいったん沈静化したように見えるが、各社ともに2024年も精製事業のあり方は課題として残る。
次世代エネルギー社会の未来像は?
一方、2023年はSSのあり方も話題となった。デザインや役割の抜本的な見直し、新規事業とのコラボレーションなど、次の方向性を模索する動きが一段と広がった年でもあった。ただ、既存燃料とEVや水素、バイオディーゼルなど、消費者が有する「乗り物」への概念、SSの存在意義などが次世代エネルギー社会のイメージとマッチングしているとはまだまだ言い難い。洗車やコーティングを主体とした給油施設がないSS、次世代車両のアピール場としてのSS、地元木材を活用した環境配慮型SS、自転車や小型電動車両のレンタルスペースを主としたSSなど、アイデアや実験段階の域を抜けきれない。消費者の心を掴むSSとはなにか、2024年も模索する日々が続く。
「2024年国内市況・西日本」へ続く
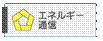 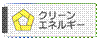
|