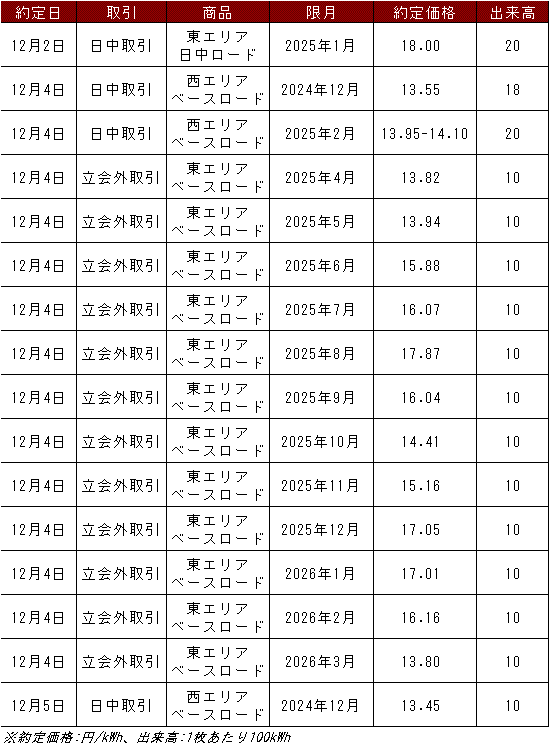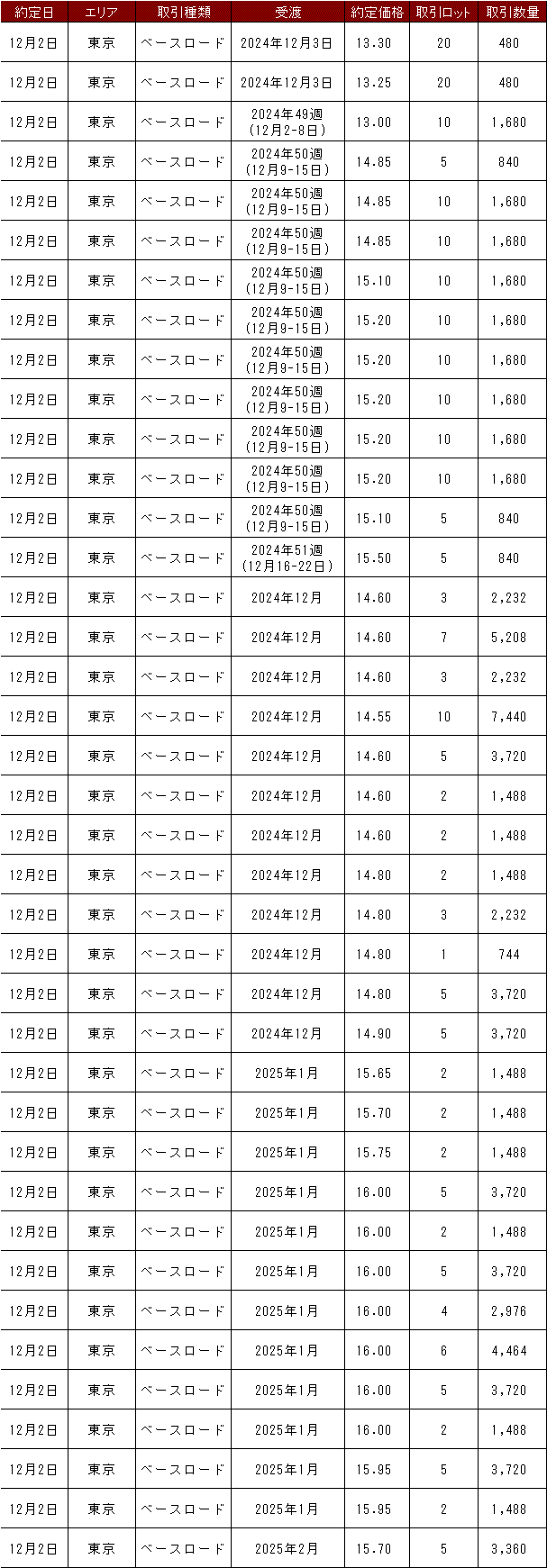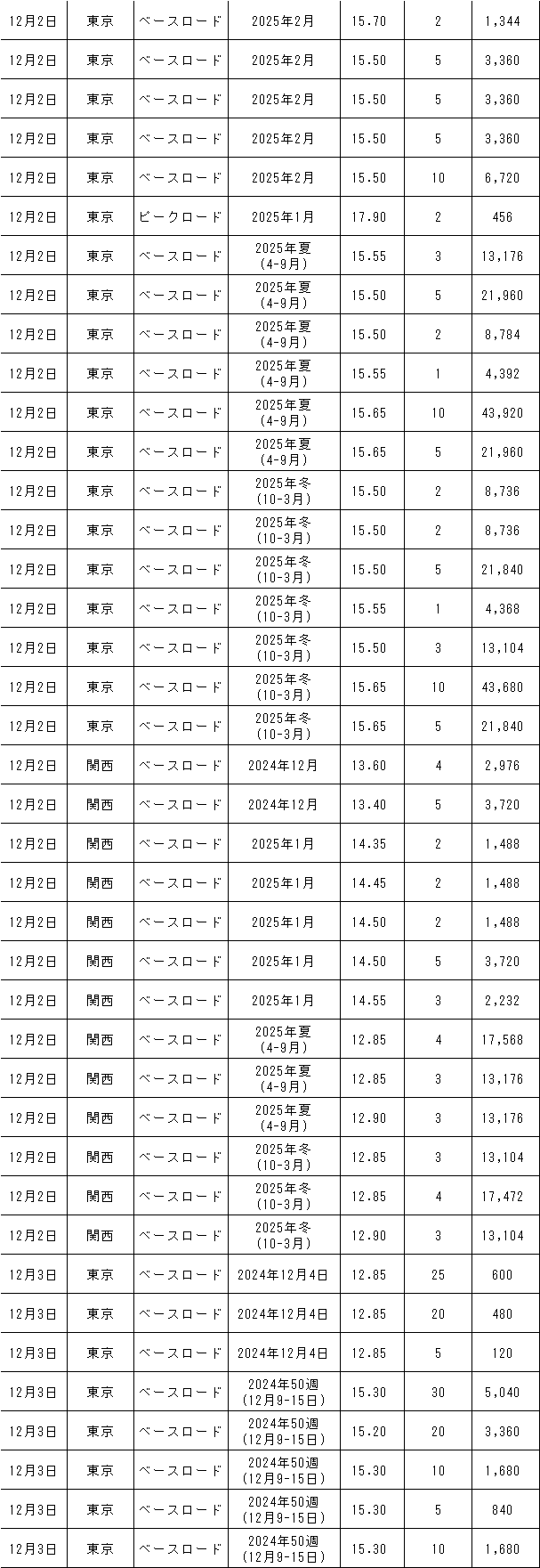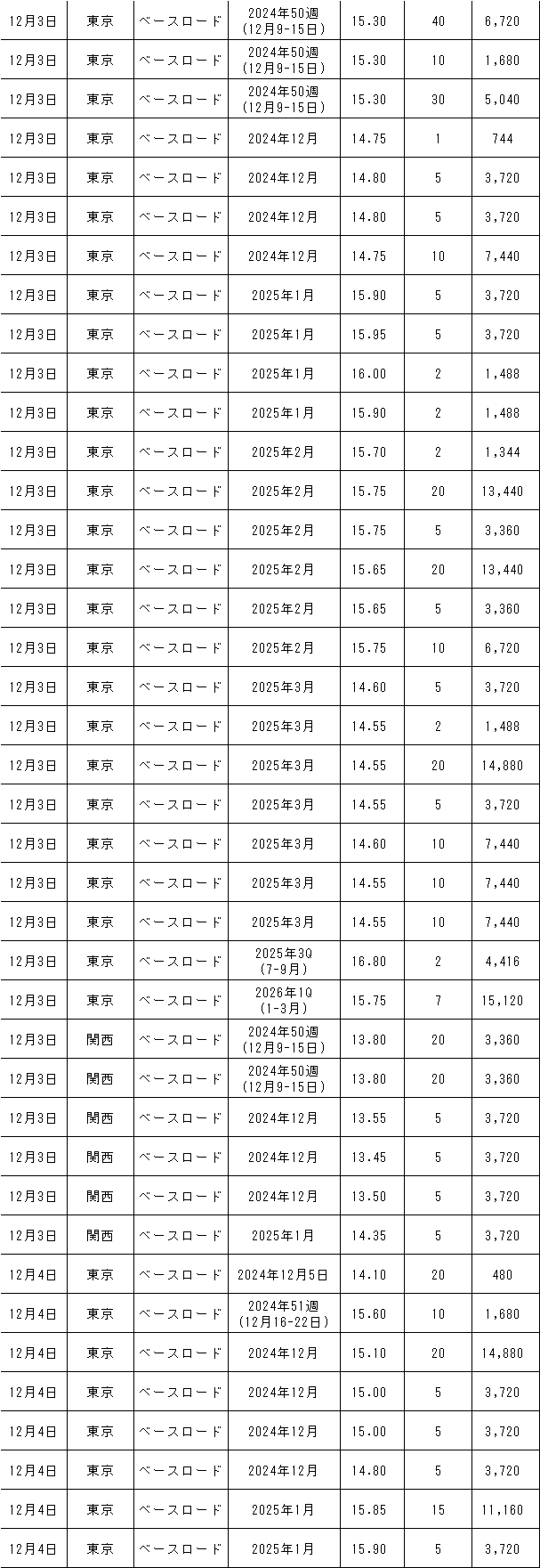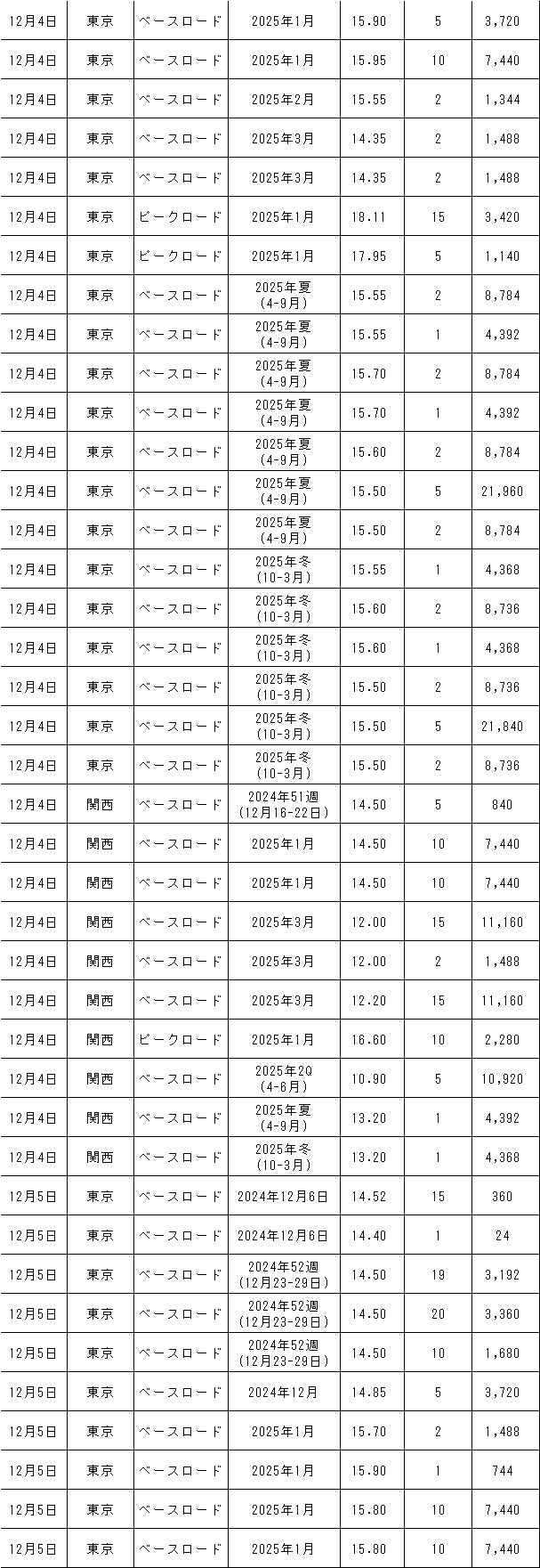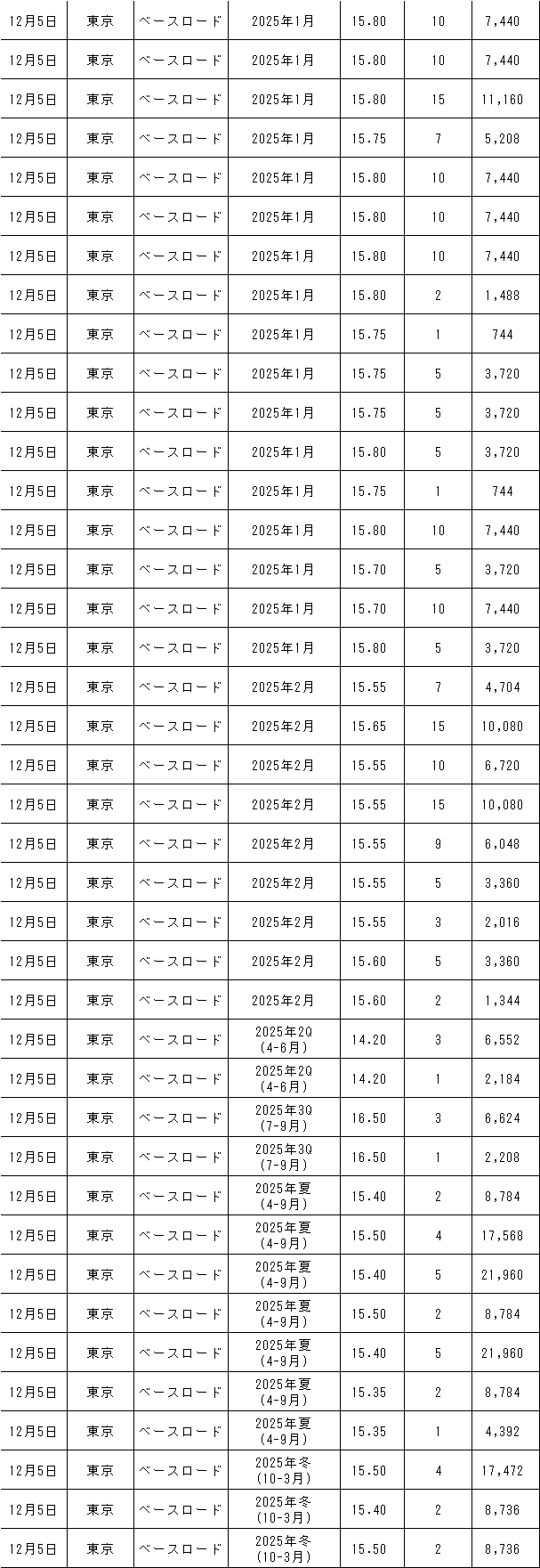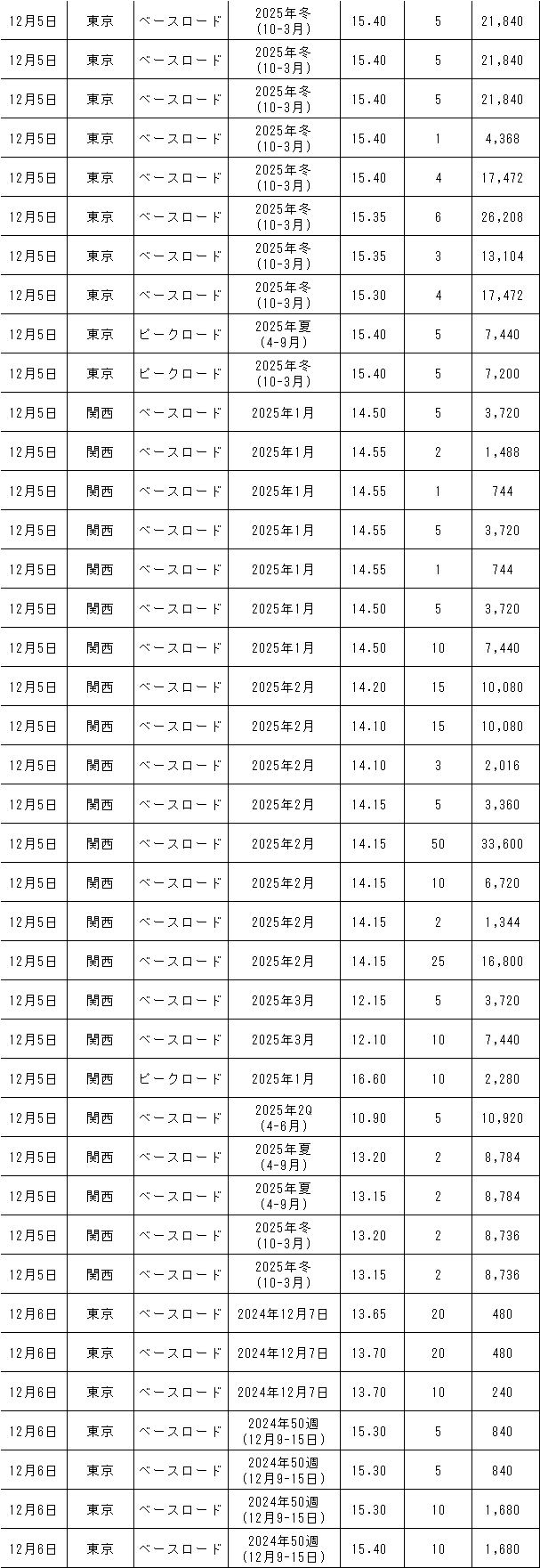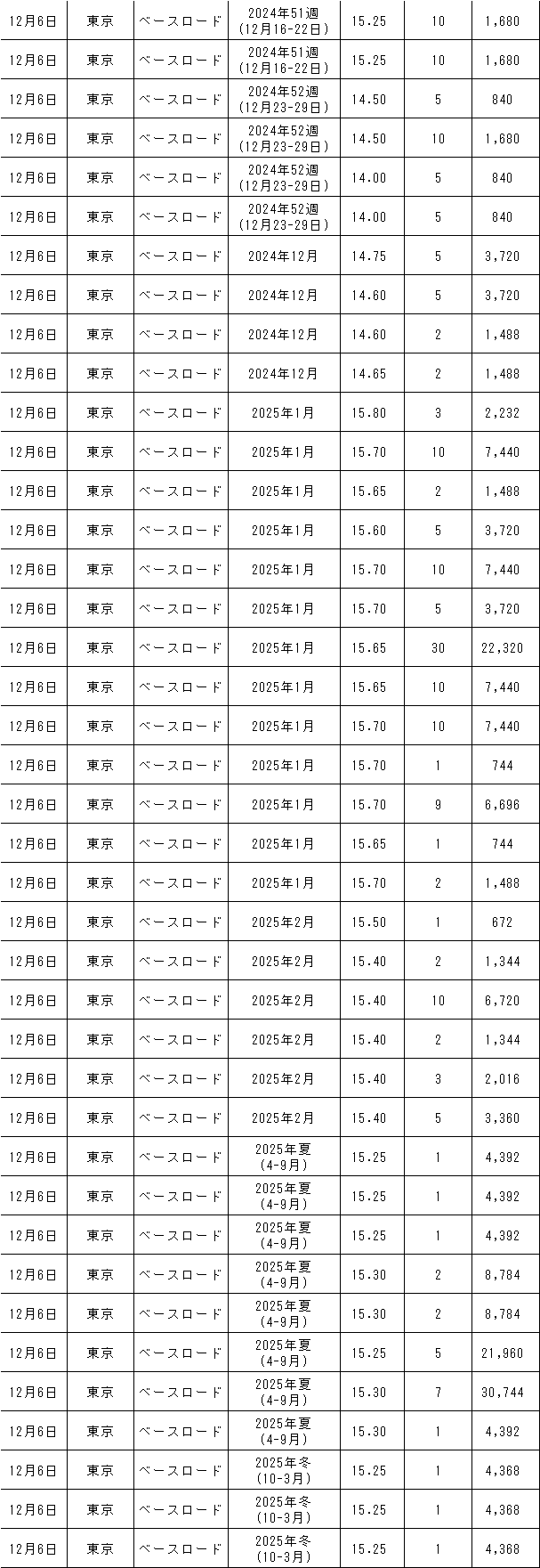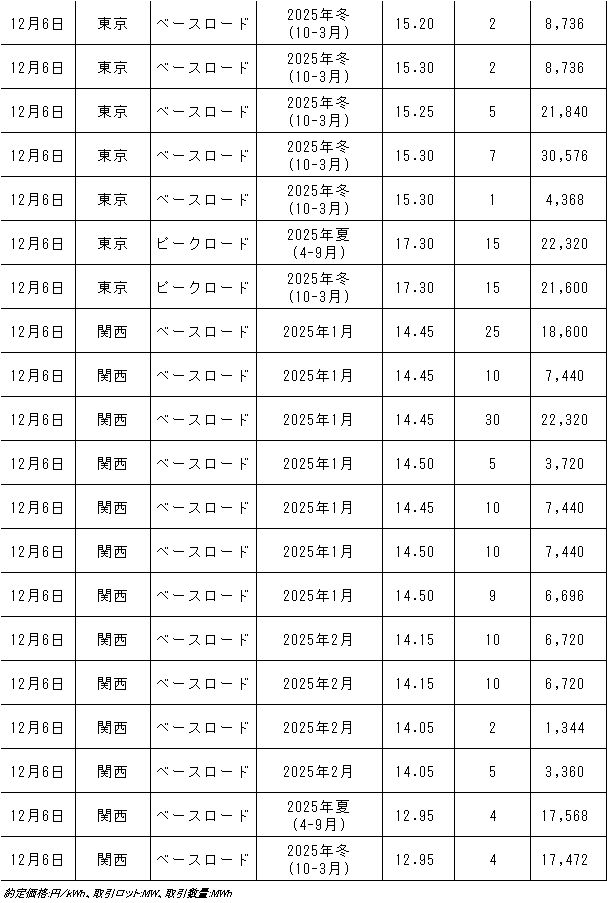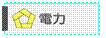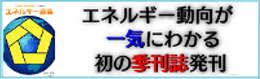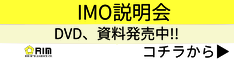電力=12月2~6日:電力スポットは前週比で続落、高めの気温と潤沢な供給で
|
12月2~6日受け渡しの電力スポット価格24時間の週間平均は、前週比で東日本(50Hz)および西日本(60Hz)ともに続落した。全国的に高めの気温で推移したほか、晴れ間の日が多くなり、太陽光発電に恵まれた。また、定期点検などで停止していた火力発電が増えたことも、弱材料となった。さらに、冬の需要期に入り、相対電源などで固めている事業者も多くなったため、市場への依存度が低下したことも価格下落を招いた一因とみられる。 また、原発の稼働も散見された。九州電力は、川内原発2号機(89万kW、PWR型、鹿児島県薩摩川内市)について、11月30日に発電を再開した。同機は9月14日から定期点検で停止し、11月28日に再起動していた。東北電力は5日、女川原子力発電所2号機(定格出力82万5,000kW、BWR型、宮城県女川町)について、同日6時に再起動した。同機は11月13日にいったん再起動した後、24日から中間停止に入り、設備・機器の安全確認、復水器内の点検や清掃を実施していた。さらに、中国電力は2012年1月27日から定期点検で停止中の島根原発2号機(定格出力82万kW、BWR、島根県松江市)について、7日に原子炉を再起動する予定。再起動後は、中間停止を挟み、12月下旬の発電機並列(再稼働)、来年1月上旬の営業運転開始を見込んでいる。 東西の主要エリアである東京と関西の電力スポットの24時間平均の値差を見ると、2日が2.15円、3日が1.44円、4日が1.18円、5日が1.38円、6日が2.16円の東高西低となった。
燃料相場は、前週末からLNGと原油が小幅高、石炭が下落した。 北東アジア市場のLNGスポットは、12月5日時点で期近の25年1月着品がmmBtuあたり14ドル台後半となり、前週末時点(11月29日)から0.10ドル程度の上昇となった。欧州の天然ガス相場が堅調に推移したため、北東アジア市場のLNG相場もつれ高となった。ただ、北東アジア市場の需給は、緩和傾向が続いており、相場の上げ幅は限定的だった。経済産業省が4日に公表した、12月1日時点の発電用LNGの在庫は189万トンとなり、前週から17万トン減少した。前年12月末時点の270万トン、過去5年平均の216万トンをいずれも大きく下回った。 豪ニューキャッスル積みの一般炭相場は、5日時点で24年12月積みがトンあたり133ドル台前半となり、前週末から4ドル程度の下落となった。需給の緩みが弱材料となった。 原油相場は、12月6日午前の時点でWTIの25年1月物がバレルあたり68ドル台前半、ブレントの25年2月物が72ドル超の水準で推移。前週末から、WTIおよびブレントともに0.3ドル程度の上昇となった。石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟国による「OPECプラス」が、1月からの増産予定を延期する見通しとなったことや、中国の景気回復観測が強材料となった。ただ、高値警戒感から売りの動きも出たため、相場の上げ幅は限定的だった。
週を通じた実勢高値は、6日に東京と中部で付けた21.00円となった。一方、実勢安値は0.01円となり、2日に四国と九州で、3~4日に九州で、5日に四国でそれぞれ付けた。 エリア別に24時間の週間平均を見ると、北海道が前週比1.85円安の12.42円、東北が同2.21円安の12.23円、東京が同1.24円安の13.79円、中部が同0.37円安の13.79円、北陸が同0.56円安の12.13円、関西と中国が同0.55円安の12.13円、四国が同2.17円安の9.60円、九州が同1.32円安の10.81円だった。 売買入札量の週間平均は、売り札が前週比20.0%増の12億1,631万930kWh、買い札が同4.0%増の9億7,274万6,160kWhとなった。約定量の週間平均は、同10.1%増の7億8,104万7,200kWhだった。
12月2~6日の9エリアの電力需要は、119億9,304万kWhとなり、前週11月25~29日の117億7,874万9,000kWhから1.8%増加した。なお、曜日を合わせた前年の12月4~8日の需要実績は125億6,827万7,000kWhで、減少率は4.6%となった。
12月2~6日の東京商品取引所(TOCOM)の約定結果は下記表のとおり。
12月2~6日の欧州エネルギー取引所(EEX)の約定結果は下記表のとおり。299件・2,048MWの約定があった。
12月第2週の電力スポットは、底上げの動きになる可能性が高い。全国的に冷え込みが強まる見通しのため、暖房需要の増加に伴い余剰電力が低下し、需給が引き締まり傾向となるとみられる。市場では、こうした需給動向を見越して、電力先物市場の週間商品を活用したヘッジの動きも活発化しており、価格上昇に対する警戒は強まっている。ただ、定期点検などで停止していた火力発電の再開も増えているため、過度な価格上昇を警戒する声は限定的となっている。
|
||||||||||||||||||||||||