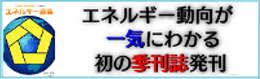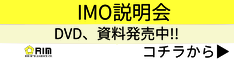新春特集=原油相場、2023年の注目材料
2022年の原油相場の動向は波乱含みの展開となった。ロシアがウクライナに侵攻したことによるエネルギー供給の逼迫を背景に、原油価格は3月に2008年7月以来の高値を更新した。ただ、年後半にかけて、米国の金利引き上げに端を発した世界景気の後退で原油需要の減少懸念を背景に、原油価格が下落。12月8日には1年ぶりの安値まで落ち込んだ。2023年の相場動向に関しては、地政学要因、中国の需要、景気動向などがカギを握るとみられる。
2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、米国をはじめとする西側諸国はエネルギー分野を対象とする経済制裁を打ち出した。ロシア産エネルギーの供給減少が決定的となる一方、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は同年3月2日の会合で、4月以降も従来の生産方針を維持すると表明。主要消費国の要請とは裏腹に、大幅増産を見送った。ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)のWTI原油先物相場、およびインターコンチネンタル取引所(ICE)の北海ブレント原油先物相場はいずれも急騰し、3月7日の夜間取引では一時、2008年7月以来となる高値(WTI:130.50ドル、ブレント:139.13ドル)を記録した。
一方、緊迫を極める東欧情勢は資源価格を高騰させ、米国を中心に世界的なインフレを引き起こした。米政府は6月の連邦公開市場委員会(FOMC)で約30年ぶりとなる0.75ポイントの大幅利上げに踏み切った。急速な金融引き締めが景気を冷やすとの警戒感が高まり、6月からは原油相場は下落に転じている。さらに、世界第2位の原油消費国である中国で2022年後半には新型コロナウイルスの感染が再拡大。中国の原油需要減少も、原油価格の下げを加速させた。
ウクライナ情勢の緊張は2023年も続くと予想される。欧州連合(EU)は海上輸送によるロシア産原油の購入をすでに禁止しており、2月には石油製品の輸入も停止する。日本など他の主要国も同様に、ロシア産石油を対象とした経済制裁を継続する公算が大きいが、足元の需給が逼迫した状態に追い込まれる可能性は低そうだと市場参加者は指摘する。欧州各国は今冬の需要期に備え、事前に天然ガス備蓄を充填させたため、不測の事態がない限りは、2023年もエネルギーの安定供給が維持されるとの見方が支配的となっている。また、中国とインドは、他国産と比べて割安なロシア産原油の購入を優先しており、2022年後半のスポット取引においては、需給に緩みが見られた。EUと主要7カ国(G7)はロシア産原油の取引価格に上限を設けた。これが、両国による購入に今後どのような影響を与えるか注目が集まる。
また、インフレの抑制には時間を要するとの見方が根強く、2023年においても世界経済の先行き懸念が原油相場の重しとなる公算が大きい。中国の需要動向も原油相場のカギを握りそうだ。同国政府は2022年11月、ゼロコロナ政策に基づく行動規制を段階的に緩和すると発表し、エネルギー需要が回復するか注目されている。