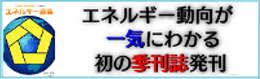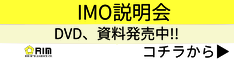新春特集=2023年の電力市場、燃料高が懸念材料
2022年の電力市場は、ウクライナ問題による燃料高に翻弄された1年となった。大手電力各社は燃料高騰や電力スポット価格の上昇が重石となり、大幅な赤字決算となる電力会社が相次いだ。さらに、新電力でも電力スポットの上昇に伴い、事業撤退の動きが進んだ。こうした電力会社の厳しい状況を受け、高圧や特別高圧の需要家は電力会社から供給を受けられなくなるところが相次ぎ、「ラストリゾート」とされる最終保障供給に頼る需要家が相次いだ。
ウクライナ問題の収束が見通せないなか、2023年も燃料高など電力各社には厳しい事業運営が見込まれるが、需要家にとっても小売料金の値上げに伴う経済負担が強まる見通しとなり、2023年も電力業界を取り巻く環境は波乱の1年となりそうだ。
2023年の電力スポット価格は、東日本で30円前後、西日本で25円前後と見通す向きが多い。その1つの根拠となっているのが23年度のベースロード市場の動向だ。燃料価格の高騰を受けて、第3回目までの時点で北海道、東京、関西ともに前年度の価格を大幅に上回った。また、東京/関西の価格差は13.06円→12.56円→7.5円と縮小気味ながら、総じて東高/西安の傾向が続いた。原子力発電所の稼働の有無によって価格差が生じたと見られ、来年度の価格見通しにも影響が出そうだ。
2023年度ベースロード取引
エリア 第1回 第2回 第3回
北海道 29.90円→約定なし→29.95円
東京 33.06円→37.67円→31.00円
関西 20.00円→25.11円→23.50円
原子力発電の稼働数は2023年に増える見通し。岸田首相は2022年8月、それまでに再稼働した10基に加え、7基の原発について2023年の「夏以降」に再稼働を進める方針を示した。7基は、東北電力の女川2号機(定格出力82万5,000kW)、日本原子力発電の東海第二(110万kW)、東京電力の柏崎刈羽6号機と7号機(各135万6,000kW、関電の高浜1号機と2号機(各82万6,000kW)、中国電力の島根2号機(82万kW)。いずれも原子力規制委員会の安全審査を通過した設備で、再稼働が実現すれば、供給力の追加規模は東日本が463万7,000kW、西日本が247万2,000kWにのぼる。再稼働が増えれば安定供給の度合いは高まるが、個別の再稼働のタイミングや全体の進捗状況次第では、電力スポット価格など短期的な波乱要因ともなりうる。また、電力会社の中には来年度からの小売料金の値上げについて、原発再稼働を織り込んでの料金水準としているため、再稼働の前提が崩れた場合、電力会社の収益に影響を与える可能性も高い。
燃料相場は高止まり傾向が続く可能性が高い。特に懸念されているのがガス価格の動向だ。ウクライナ問題の影響により、欧州ではロシア産天然ガスからLNGへ切り替える動きが見られ、LNGタンカーの発注も急増。近年、原油の代替燃料としてLNGは注目されているが、激しいLNG争奪戦が懸念される。
石炭相場も下落が見通せない状況となっている。脱炭素化の流れで石炭消費の削減をする動きが強まった影響により、閉山に追い込まれた炭鉱が多く、今後も供給は増える見通しにない。ロシア産エネルギーへの依存が高い欧州では、石炭需要も増加している。このため、来年度も石炭需要は低減しない可能性が高く、相場は下がりにくい状況が続くと見られる。
燃料相場の動向や原発の再稼働計画が流動的で、電力価格の先行きに不透明感が強まるなか、先物市場を通じた価格ヘッジニーズは今後もますます強まることが予想される。実際のところ、欧州エネルギー取引所(EEX)を通じた2022年1~12月期における日本の電力取引量は6,000GWhを大きく上回る見通し。12月の約定量が大きく伸びれば、21年1~12月期の取引実績である6,605GWhを超えて、過去最多を更新する可能性もありそうだ。
また、東京商品取引所(TOCOM)でも、2022年10月末時点で電力先物市場への参加者が154社に増えているほか、立会外取引を中心にまとまった数量での約定が増えている。