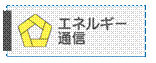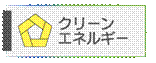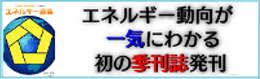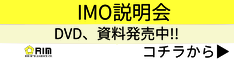特集記事 世界の炭素価格付け、2022年の潮流 その1
|
世界の各地でカーボンプライシング(炭素価格付け)の動きが広がる。ただ、その年ごとの進展は必ずしも一様ではない。 世界銀行の年次報告によると、2022年、世界の炭素クレジット市場は量的には減少。一方で、排出量取引を導入する地域はわずかながら拡大した。排出量取引の価格は上昇傾向をたどる。炭素税と排出量取引による公共機関の収入は増加した。 〇炭素クレジットの発行量、4.75億トン 炭素クレジットの世界全体の発行量は2022年、二酸化炭素(CO2)換算で4億7,500万トン。 炭素クレジットの柱であるボランタリー(民間主導)クレジットは2億7,500万トンと前年比22%減少した。他方で、公的なクリーン開発メカニズム(CDM)による炭素クレジットが増加し、全体を下支えした。 例えばベラ(Verra)が運営する民間で世界最大の炭素クレジットであるVCSでは、2022年は前年に比べ申請が243%、承認が90%とそれぞれ増加した。 申請の急激な増大により、炭素クレジットの発行に遅滞が生じた格好。とりわけ新規の申請者による案件の審査は、修正などで通常よりも多くの時間を要するため、クレジット発行が遅れる大きな要因となった。 加えて、インドネシアなど一部の国による炭素クレジット発行の制限も2022年の供給を減少させた。 足下では供給網の障害が問題だが、半面、長期的な視点に立てば、様相は異なる。炭素クレジットの運営者や申請者が障害を適応にすれば、水面下に沈んでいた炭素クレジットが今後、市場に供給される可能性があることを意味する。
民間主導クレジットの発行が減少する中、国連気候変動枠組み条約に基づくCDMの炭素クレジットは2022年に増加し、全発行量の30%以上を占めた。 CDMは、先進国が発展途上国のCO2排出量削減への取り組みを資金や技術で支援し、達成した排出量削減分を両国で分配できる制度。1997年の国連気候変動枠組み条約第3回条約国会議(COP3)で採択された京都議定書に盛り込まれた。 世銀は、2021年10月開催のCOP26でCDMの一部を各国の排出削減目標(NDC:パリ協定に基づき2016年11月発効)に使用できることが決定されたため、CDMによる炭素クレジット発行が2022年に活発化したとみている。 NDCに使用できるようになったことに加えて、CO2排出の自主的な埋め合わせ(オフセット)の需要も、CDM活用を促した面もあるという。
〇温室効果ガスの約23%を網羅 世界で導入されている炭素価格付け制度は今年4月時点で73件と、前回報告時より5件増えた。73件の制度により、世界で排出される温室効果ガスの約23%が網羅される。報告書が最初にまとめられた10年前の7%から16ポイント上昇した。ただし、過去1年でみると、増加幅は1%未満にとどまる。 約23%の内訳は、排出量取引制度(ETS)が18%、炭素税が5.5%。過去1年間で増えた5件のうちオーストリアは、道路輸送とビル・建物、農業の燃料消費を対象とする(欧州連合では現在、対象外)ETSを導入した。米ワシントン州もETSを開始。メキシコのケレタロ州とメキシコ州、ユカタン州は炭素税を導入した。
|