|
【供給】
原油の供給が逼迫する事態は避けられそうだ。むしろ、米国産原油の生産は拡大傾向にあり、世界的な供給過多に直面する可能性が排除できない。
石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は11月30日、2024年1~3月にかけて日量220万バレルの自主減産に取り組むことで新たに合意した。サウジアラビアとロシアは、このうち日量150万バレルの減産を担う。サウジアラビアは、2023年7月に開始した日量100万バレルの自主減産を2024年3月末まで継続、ロシアは減産枠を従来から同20万バレル拡大し、日量50万バレルの供給削減を実施する。
もっとも、OPECプラスによる自主減産の実効性に対しては、懐疑的な見方を強める市場関係者が少なくない。自主減産は各国の裁量に左右されやすいうえ、アンゴラやナイジェリアなど一部の加盟国が生産枠の縮小に消極的な姿勢を示しているからだ。今回OPECプラスが、2022年11月から実施している協調減産の強化について合意に至らなかったことは、「各国の足並みがそろっていない証拠として受け止められた」(大手証券会社のエコノミスト)。今後もサウジアラビアは石油市場の安定化に奔走するだろうが、OPECプラスが加盟国の満場一致で減産強化を実現させるには困難を極めそうだ。
また、米国産原油の生産が増加傾向にあることも度外視できない。米エネルギー情報局(EIA)の統計によると、米国の原油生産量は2023年9月に日量1,320万バレルと過去最高水準に達した。米国産原油の供給が過多になるとの見通しが強まりつつある。
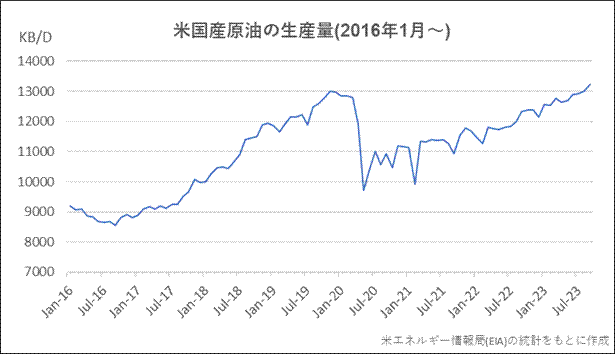
【需要】
2024年には、石油需要の落ち込みが顕著に表れる可能性がある。石油消費大国の需要減少に悲観が広がれば、原油相場に一段の下方圧力が加わる展開も視野に入る。
石油の需要動向を語るうえで無視できないのが中国だ。同国では不動産分野の不況が深刻化し、パンデミックからの経済回復が妨げられている。中国国家統計局が発表した11月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は49.4と、好不況の判断基準とされる50を2カ月連続で割り込んだ。2023年4月以降、同国の製造業PMIが50を上回ったのは9月のみであり、市場には失望が広がっている。同国の原油輸入に顕著な落ち込みは見られないものの、世界の石油需要を牽引する中国の景況次第では、原油相場が急激な下押し圧力に見舞われる展開も想定される。
さらに、欧米ではインフレ抑制的な金利政策が長期化する可能性が指摘されている。米連邦準備制度理事会(FRB)は2022年3月に利上げを開始。2023年5月にかけて9会合続けて政策金利を引き上げた。欧州中央銀行(ECB)は、2023年9月に10会合連続となる利上げを決定。2024年には利下げが視野に入るが、「高金利政策に伴う欧米諸国の景気後退はほぼ既定路線」(大手証券会社のエコノミスト)。景気の下振れリスクが払拭されず、世界の石油需要が落ち込むシナリオが捨てきれない。
2024年11月には、米国大統領選挙が実施される。共和党のトランプ前大統領が政権に返り咲いた場合には、環境対策規制が撤廃・緩和され、化石燃料の使用を最大化する政策が数多く打ち出されるだろう。中国やロシアに対する強硬外交、対イラン制裁の強化は石油価格の高騰を招きかねない。石油需要の転換点となりうるか注目が集まる。
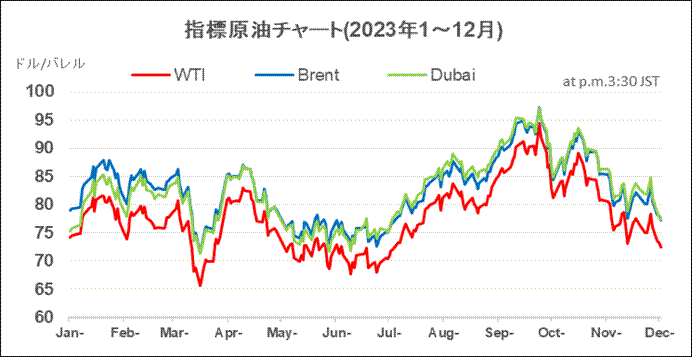
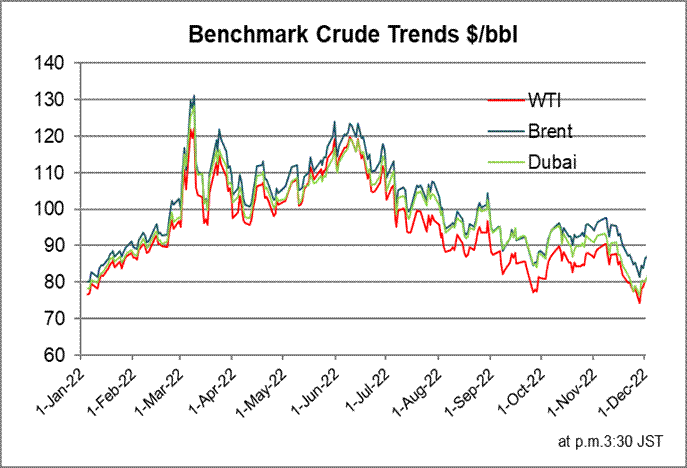
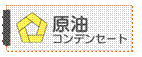
|