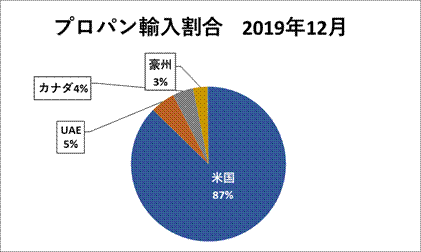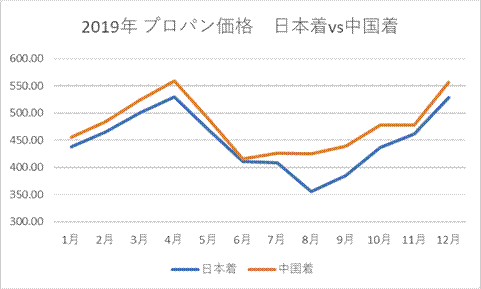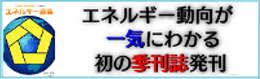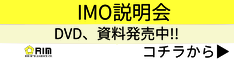LPG=ENEOSとJGEが4月に仕切り価格体系を変更
|
液化石油ガス(LPG)の大手元売りENEOSグローブとジャパンガスエナジー(JGE)が4月から、国内の卸業者に販売する価格(仕切り価格)の計算式を変更することが複数の市場関係者への取材で分かった。元売り各社は現在、プロパンの仕切り価格を算出する際に、アラムコCPと米モントベルビュー市況という二つの国際指標価格を加重平均した値を採用している。ENEOSとJGEは今後、米国産プロパンの輸入量が急増している近年の実情に合わせ、両価格の割合を従来の「75%対25%」から「70%対30%」に変更し、米モントベルビュー市況の比率を高める方針だ。また、フレート代の算出方法に関しても、中東フレートが70%、北米フレートが30%の割合に変更される。同じLPG元売りのアストモスエネルギーとジクシスは2017年からアラムコCPとモントベルビュー市況の割合を「70%対30%」に設定しており、これで4月以降は大手元売り勢の足並みが揃う形になる(下表参照)。
表:従来の仕切り価格体系
表:4月以降の仕切り価格体系
ENEOSグローブの関係者は変更の経緯を「米国産プロパンの輸入割合が増えている実態に合わせた」と説明。ただ、一部の卸業者は以前から、プロパンの国別輸入割合で米国が70%以上を占めている点に着目し、仕切り価格におけるモントベルビュー市況の比率を25~30%から、さらに高めるべきと主張していた。財務省が発表した2019年12月の貿易統計速報によると、米国産プロパンが日本の輸入量に占める割合は87%を占める(下図参照)。大手元売り勢がモントベルビュー市況を仕切り価格に導入し始めた2017年6月時点でさえ、米国産プロパンの輸入割合は日本全体の52.3%に達していた。
図:プロパン輸入割合 2019年12月
こうした卸業者からの意見に対しては、ENEOSグローブに限らず、他の元売り関係者からも「米国産プロパンの輸入割合が増えているのは海外市場での取引で結果的にそうなっているだけ。米国や中東の供給業者と結んでいる元々の契約数量を基本に考えると、米国産プロパンの輸入割合は依然として全体の3割程度」との声が寄せられている。市場関係者によると、LPGの海外市場では2018年4月以降、米中貿易摩擦の影響で中国が米国産LPGの輸入を事実上取り止めたため、中国輸入業者と日本元売りの間で、オリジンスワップ(原産地交換)取引が頻繁に実施されてきたという。こうした取引の例としては、中国輸入業者が抱える米国産LPGと、日本元売りが保有する中東産LPGを交換するケースが挙げられる。この場合、日本元売りが中東産カーゴを輸入せずに他国の輸入業者やトレーダーに手放し、代わりに米国産カーゴを受け取るため、これが統計上、米国産プロパンの輸入比率を高める要因になっていた。
ただ、LPG消費量の多い中国やインド向けの需要が中東産カーゴに集中したことで、米国産カーゴは相対的に安い価格で調達することが可能になった。2019年1~12月におけるCFR日本着相場とCFR中国着相場のそれぞれのプロパン価格を比較すると、中東産カーゴを主に輸入している中国着価格の方がトン当たり28.35ドル高い(下図参照)。そのため市場関係者間では、「日本元売りにとっては価格面でもオリジンスワップに応じる利点があった」(欧トレーダー)という見方が根強い。
図:2019年1~12月における日本着プロパン相場と中国着相場の比較
一方、ENEOSグローブとJGEは4月以降モントベルビュー市況の比率を高めると同時に、米国産プロパンにかかる調達経費を引き下げる方針だ。JGEは4月からトン当たり3ドル、ENEOSグローブは5月から同7ドル(4月からトン当たり8ドル引き下げた後、5月からパナマ運河の通行料値上げにより1ドル引き上げ)、それぞれ現行の仕切り価格から差し引く。米供給業者から購入している長期(ターム)契約の基地使用料が、以前のガロン当たり14セントから引き下げられているためだ。これには海外市場でのオリジンスワップによって得られた利益などを、卸業者に還元しようとする意図も垣間見える。
この他、船舶用重油の環境規制が強化され、バンカーコストが上昇していることから、アストモスが米国産プロパンの調達経費を現行のトン当たり105ドルから同110ドルに引き上げるとの噂も昨年末に流れた。同社はこれを否定したものの、LPGの国際市場情勢が毎年のように目まぐるしく変わるなか、日本の元売り各社が適正な収益の確保とその還元を目指して、最適な仕切り価格体系を模索する日々は続きそうだ。
|