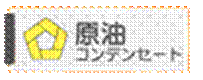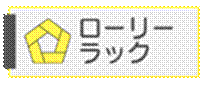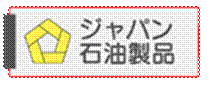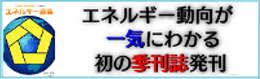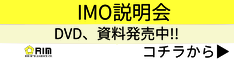どうなる今冬のエネルギー供給2025(1)-原油 国内
|
冬の暖房需要が意識され始める時期だが、2025年冬のエネルギー動向について、リム情報開発の各レポート担当記者が、8月中旬時点での見通しをまとめた。 【原油】 2025年冬の原油供給は、OPECプラスと米国の生産動向が大きな影響を及ぼす。OPECプラスは、25年4~9月にかけて段階的に減産を解除し、日量合計で約246.7万バレルの増産を実施する見通しとなっている。この増産により、有志8カ国が行ってきた日量220万バレルの自主減産は完全に解除されることになる。5月以降は当初の計画を上回るペースで生産が拡大しており、OPECプラス全体としては今後の需給動向に応じて、生産量を柔軟に調整する方針を示している。
一方、米国ではリグ稼働数の減少や掘削効率の低下が続いており、生産の勢いに陰りが見える。米国エネルギー情報局(EIA)は、25年第2四半期をピークに原油生産が緩やかに減少し、26年末までに日量約10万バレルの自然減産が進むと予測している。これにより、米国は年間ベースでも供給減少に転じる可能性がある。戦略石油備蓄(SPR)は高水準を維持しているものの、放出には政治的・実務的制約があり、冬季の需給調整には即効性が乏しい。
さらに、イスラエルとイランの対立を背景とした中東情勢の不安定化も続いており、地政学的リスクは依然として価格変動の要因として無視できない。これらを踏まえると、25年冬の原油供給は表面的には安定しているが、不透明感とリスク要因を内包しており予断を許さない。
冬場のローリー配送力確保が焦点 国内石油市場では、昨年に引き続き「物流の2024年問題」を背景とする冬場の配送力確保が大きな焦点となりそうだ。灯油需要が増える冬場は燃料輸送量が増加する一方で、同問題によるドライバー不足でタンクローリーの配送力が逼迫しがちだからだ。実際、昨冬は寒冷地を中心に配送力不足が表面化した。石油卸業者の間では配送力を保つべく、すでにローリーの定期チャーターを増やす動きが出始めている。冬場に配送力を発揮できるのは「相当なステイタスになる」(北海道を拠点とする石油ディーラー)。 ただ、定期チャーターは一筋縄には行かない事情もある。卸業者は冬季の季節チャーターを希望するが、石油運送会社は年間チャーターを求める傾向が強い。冬季だけの「いいとこ取り」は避けて欲しいと考えているためだ。卸業者にとり、年間チャーターを増やすと、灯油需要が萎む夏場にローリーを持て余すリスクが高まる。このためチャーターの必要性を意識しつつも、現段階では模様眺めに徹する卸業者も少なくない。また運送会社はドライバー確保という課題を抱えており、卸業者がチャーターを要望しても、人手不足の観点から契約を即断できず、話が宙づりになるケースもある。 ガソリン、軽油に課されている暫定税率廃止議論の先行きも、冬場の燃料市場を左右するポイントだ。7月20日の参議院選挙では、野党が求めるガソリンの暫定税率廃止に消極的だった自民党が大敗し、廃止の可能性がにわかに現実味を帯び始めた。 8月に入り具体的な動きが表面化。1日に野党7党が議員立法ガソリン暫定税率廃止法案(租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案)を衆議院に提出した。今回の法案はガソリンの暫定税率廃止のみを対象としており、地方税扱いの軽油は外されている。監督官庁の資源エネルギー庁および総務省も「暫定税率廃止の対象はガソリンのみで、軽油は対象外」との認識を示した。市場ではガソリンと軽油は同時並行で暫定税率の廃止を見越していた節もあっただけに、今後の販売計画や在庫管理に影響を及ぼすのは必至だ。 ただ、現時点で暫定税率廃止の有無や時期はまだまだ流動的。さらに暫定税率の廃止が見送られた軽油、暫定税率がない灯油、重油の扱いがどうなるのかも未知数と、課題は山積。提出された法案によると、11月1日付でガソリンの暫定税率は廃止と謳っている。一方で11月は北海道や東北地区で灯油需要期に入り、灯油価格に敏感な時期となるため、ガソリン価格との整合性、既存の補助金の継続有無なども市況を見るうえで大きな材料となってくる。暫定税率廃止、補助金の扱い、冬季需要期など、政府の方針次第では各油種の買い控えや買い控え後の反動的な需要急増なども想定される。こうした時期に海外原油相場の大きな動きが重なった場合、予想外の相場変動が起こり得ると構えたほうがいいかもしれない。
|