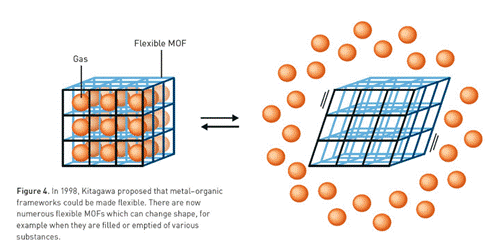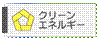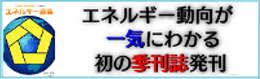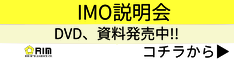ノーベル化学賞=北川進氏受賞、脱炭素にも応用可能な金属有機構造体
|
スウェーデン王立科学アカデミーは8日、2025年のノーベル化学賞を京都大学の北川進(74)特別教授ら3氏に贈ると発表した。共同受賞者は、豪メルボルン大学教授リチャード・ロブソン氏(88)、米カリフォルニア大学バークレー校教授オマー・ヤギー氏(60)。受賞理由は新しい分子アーキテクチャーである「金属有機構造体の開発」となっている。
「金属有機構造体(metal-organic frameworks:MOF)」とは、金属イオンでつながれた分子と分子の間に、部屋のような隙間を複数持つ多孔室材料で、そこに意図した分子を出入りさせることができる。さらに、内部に広大な表面積を得る特長があり、数グラムでサッカー場1面に匹敵する広さを持つMOFもあるという。3者の共同研究ではなく、それぞれに研究が進められた。まず、ロブソン氏が銅イオンと4本の「腕」(原子価)を持つ分子を結合させ、MOFの基礎となる分子モデルを1989年に発表した。この分子モデルは不安定で壊れやすかったが、その後、1992年から2003年にかけて、北川氏とヤギー氏が安定した構造のMOF製造方法を確立していく。1997年には北川氏が、メタンや窒素、酸素といったガスの吸収や放出が可能な、呼吸しているかのように柔軟なMOFを発表し、社会実装への可能性を示した。ヤギー氏はMOFの耐熱性や安定性に優れたMOFの成果を出した。
3者の発見を足掛かりに、世界中の化学者が数万種類のMOFを開発。水から有機フッ素化合物(PFAS)などの有毒物質を除去する、砂漠の空気から水を生成する、大気や排ガスからの二酸化炭素(CO2)を回収する、化学反応の触媒にするといった、環境やエネルギーなど人類の課題となる多くのテーマに研究機関、企業が応用している。国内でも、レゾナックと日本製鉄、京大を含む6つの国立大学が共同で、製鉄所や工場などからのCO2回収実証を、国からの支援を受けて2022年から30年まで進める。生産コストが低いというMOFの特長を活かし、2030年には1トンあたり、2000円台の分離回収コストを目指す。
また、大阪ガスもMOFを活用し、e-methne(合成メタン)の製造に必要となる、CO2を大気などから回収するDAC(Direct Air Capture)技術を開発中だ。大量生産が可能なファイバー型としたMOFのCO2吸着材を米ジョージア工科大学と共同開発を進める。9月に千葉幕張メッセで行われた、「2025 スマートエネルギーウィーク【秋】」の大阪ガスブースでは、実際にDAC装置を稼働させ、CO2回収の様子を展示した。
ノーベル賞の授賞式は12月10日にストックホルムで開催され、賞金である1,100万スウェーデンクローナ(約1億7,000万円)を3者で分ける。
1998年北川進氏が開発したMOFのイメージ (ノーベル財団発表資料)
大阪ガスが展示したMOFを活用したDAC装置
|