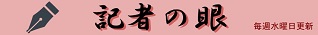第336回 (2026年2月25日)
1月下旬、米国を襲った大寒波「Fern」は、世界最大のガス生産国が抱える構造的な脆弱性を容赦なく白日の下にさらした。氷点下の寒気はテキサスからルイジアナ、さらにメキシコ湾岸の主要ガス田へと広がり、パーミヤンやヘインズビルといった南部の生産拠点では、ガス井やパイプラインが相次いで凍結した。
とりわけ冬への備えが不十分な南部では被害が深刻だった。需要が最も高まる季節に、供給力が一気に失われるという皮肉な展開である。一方、暖房需要の高まりに加え、AIデータセンター向けの電力需要も重なり、需給は一気に逼迫。代表的な米国ガス指標であるヘンリーハブ先物は、mmBtu当たり7ドルを超え、2022年9月以来の高値を記録した。
これまで米国のガス価格は、欧州や北東アジアのLNG相場とは距離を保った動きを見せてきた。しかし米国はいまや世界最大のLNG輸出国であり、欧州のエネルギー安全保障は米国産LNGへの依存を深めている。この冬、欧州のガス価格や北東アジアのLNGスポット価格がヘンリーハブに連動して上昇したのは、その象徴だ。
もっとも、足元ではヘンリーハブだけが突出して高値圏にあるようにも映る。今後、世界的にLNG供給が増えれば、割高となった米国産LNGの引き取りがキャンセルされるリスクもくすぶる。LNG市場では依然としてオランダのTTFが注目されるものの、寒波一つで世界を揺らした今回の出来事は、ヘンリーハブの影響力が新たな段階に入ったことを示している。
(志賀)