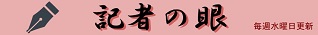第314回 (2025年9月17日)
中国福建省に住む姪が結婚し、地元の役所で戸籍登記の手続きを済ませた。その際、結婚祝い金として1,500元(約3万円)の一時金を支給された。この話しを聞き、中国の子育て支援についても調べてみた。中国は日本同様、若者の結婚離れ、少子高齢化が急速に進んでいるためだ。
私の出身地である福建省では0~3歳児に年間3,600元(7万5,000円)の手当てが支給されるほか、全国では公立幼稚園の無償化、育児休業の拡充など多くの支援策が導入あるいは検討されているようだ。「出産・子育ては家庭だけでなく社会全体で支える」という理念のもと、少子化の流れを防ぐための取り組みが続いている。
中国では1980年代、人口急増を防ぐ手立てとして、漢民族に対し一人っ子政策を導入。長年にわたり人口抑制を図ってきた。ところが今度は出生率の低下や少子高齢化が進み、男女比率の歪みなどの社会課題が浮上した。政府は2016年に二人っ子政策、21年に三人っ子政策など出産制限を段階的に緩和。それでも若者の結婚・出産への意欲は戻らず、依然として出生率は低水準に留まる。
出生率低下には、社会基盤の整備が追い付かなかったり、若者のキャリア志向、結婚式や子育て・教育費の負担増も考えられる。政府の支援だけでは追い付かず、家庭や企業、社会全体の意識変革が欠かせないだろう。
政府のさまざまな政策、社会の変化など、その背景には複雑な事情がある。記者として私が追いかけるのはエネルギー価格だが、その変化の背景を深く理解する必要があるとあらためて感じた。
(方)