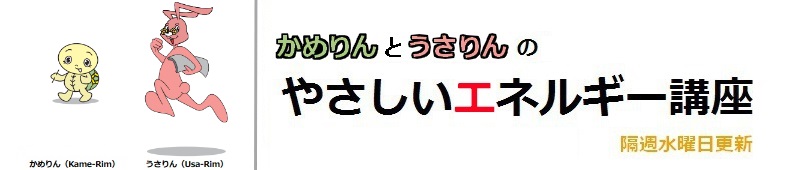ホーム > やさしいエネルギー講座
やさしいエネルギー講座
第29回 銭湯へ行こう!~エネルギーからみる銭湯の歴史~の巻(2013年7月5日)
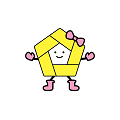
富士山がついに6月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録されたわね!

お~登録されたのか。世界遺産の登録は2011年の岩手県の平泉(文化遺産)、東京都の小笠原諸島(自然遺産)以来だから、約2年ぶりだね。
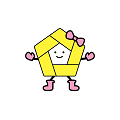
今年の夏に、一緒に登りに行こうよ。

いや~僕は登山は・・・同じ富士山を見に行くなら銭湯がいいな。これから夏で暑くなるし、きっと気持ちいいぞ~。
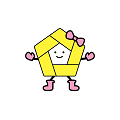
も~お兄ちゃんったら若いくせに。でも、銭湯の富士山も情緒があっていいわよね。

そうそう。それに、僕がいつも行く銭湯は薪でお湯を焚くところだから、お湯もやわらかい感じがして気持ちいいんだよ。
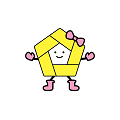
薪で焚くとお湯がやわらかい?それ本当?

いや、まあ、よくそういう風に言われるってだけのことなんだけどね。でも、昔ドラム缶に湯をはって薪で焚いたお風呂に入ったときは、とても気持ちよかったなあ。あれは電気やガスではない、薪だからこそ味わえる気持ちよさなんだ!
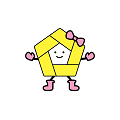
ドラム缶って・・一体どんな生活してたの。お兄ちゃん。

まあ、今では薪を燃料にする銭湯はだいぶ少なくなってきているけどね。1950年代頃まで、銭湯の燃料は主に薪やおがくずで、戦後の薪がない時なんかは石炭も使われていたんだけど、その後は重油や廃油が主流になったよ。重油っていっても、正しくはA重油で、漁船の燃料などに使われるのと一緒だね。
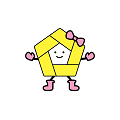
へえ~、どうして薪や石炭を燃料にするのをやめてしまったの?

その当時は、薪に比べて重油の方が安かったからさ。それに、薪だとどうしてもお湯を焚くのに手間がかかってしまう。廃材を仕入れて、それを切りそろえて積み上げるだけでも重労働だし、釜に薪をくべて湯を沸かすのも大体2時間半はかかるんだ。湯を沸かした後だって、定期的に釜に薪を入れなきゃいけないしね。さすがにオイルショック後には重油から薪に戻る動きもあったみたいだけど、今は銭湯を経営する人はどんどん高齢になっているから、こうした重労働は大変というのもあって、主流はまた重油になっているんだ。
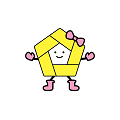
なるほど。第22回でも重油について話したけど、発電燃料以外にも重油は使われているのね。でも、昔に比べて原油の価格は今すごく高くなっているから、重油にかかる費用も相当高くなっているんじゃないかしら。

そのとおり。これもすでに第17回で話したけど、オイルショック後の逆オイルショック時では、原油価格は1バレル当たり20ドルを下回っていたんだ。それが2000年代に入るあたりから徐々に上昇し始め、特に2008年に初めて100ドルを超えている。銭湯でも、この原油価格の高騰の影響を受けて、燃料を重油からより価格変動の小さいガスへと切り換える動きが広まったんだ。今では東京都内にある銭湯の多くが、都市ガスを利用しているよ。
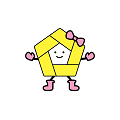
じゃあ、今は重油を使うところもだんだんと減っているのね。それに、最近はアベノミクス効果で円安が続いているから、輸入原油の価格は一段と高くなるでしょうね。重油を使うところはますます厳しい状況になりそうね。

そうだね。銭湯の数は年々減少していて、その原因は家庭にお風呂が普及したことが大きいけど、こうした燃料価格の高騰によって経営が難しくなったという面も大きいんだ。東京都公衆浴場基礎資料によれば、1960年代半ばに東京都内に銭湯は2,600軒以上あったそうだけど、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合のホームページでは現在、都内で営業しているところはおよそ750軒程度にまで減少してしまっているんだ。
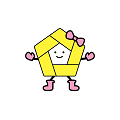
なんだか寂しいわね。昔ながらの日本の文化も、燃料事情にずいぶん影響を受けているのね。でも、銭湯の燃料だけをみても薪から油、そしてガスと、私たちのエネルギー源がどう変化していったかがわかって勉強になったわ。

おっ、いいことを言った。よし、お兄ちゃんが銭湯でビン牛乳をおごってあげよう!
|
このコーナーに対するご意見、ご質問は、リムゾー&リミーまで 電話 03-3552-2411 メール rimzo@rim-intelligence.co.jp |
クイズに挑戦してみよう!
今回の
「やさしいエネルギー講座」
から出題!
「やさしいエネルギー講座」
から出題!
銭湯でお湯を沸かす際、主に使われる油の種類は?
正解と思ったボタンを押してみよう。
エネルギーの知識をさらに深めたい人は、一般社団法人日本エネルギープランナー協会の検定に挑戦してみよう!
(リム情報開発は、一般社団法人日本エネルギープランナー協会を応援しています)